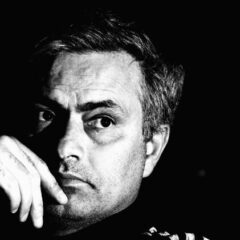変化するイタリアサッカー “カテナチオ”の印象は薄れてきた
今季セリエAで快進撃を披露するラツィオ photo/Getty Images
続きを見る
カテナチオとは、本来はリベロの起用を前提とした用語だ。リベロの発祥はオーストリアで、マンマークのDFの背後をカバーするフリーバックの動きが門に差し錠を通す動きに似ていたことから閂(かんぬき)と呼ばれていた。それがイタリアに伝わり、イタリア語で閂を意味するカテナチオと呼ばれるようになった。
つまり、カテナチオはフリーのカバーリングバックであるリベロとともにあるプレイスタイルなのだ。そういうわけで、リベロがいなくなった 1990年代にはカテナチオも消滅したことになる。ただ、堅固な守備力を軸にした戦い方や、いわゆる「1-0の美学」と呼ばれた試合への 向き合い方は、リベロが消滅した後 もイタリアの伝統として受け継がれてきた。
それは1980年代の終わりにACミランがゾーンディフェンスとプレッシングを組み合わせた守備戦術で新しい時代の幕を開けて以後も変わらなかった。従来のリベロ+マンツーマンディフェンスでなく、ゾーンディフェンスを導入したアリゴ・ サッキ監督のミランは革命的だったが、サッキがイタリア代表監督として同じ戦術を導入しても、やり方が変わっただけで、イタリアの印象は依然として堅守のままだったのだ。
今季のセリエAではアントニオ・コンテ監督の率いるインテルが、イタリアの伝統を受け継ぐチームである。 しかし、長く一強時代を築いてきた ユヴェントスはマウリツィオ・サッリ監督を迎えている。サッリの招聘はプ レイスタイルの変化を意味するわけで、これまで以上にパスワークを重視するようになった。
第23節終了時点で3、4位につ けているラツィオ、アタランタにも“カ テナチオ”のイメージはない。
ラツィオの中盤は攻撃型3枚 指揮官のこだわり見える構成に
セリエAでは異例とも言える長期政権を築くインザーギ監督。ラツィオ躍進の立役者であることは 間違いない photo/Getty Images
続きを見る
ラツィオを率いるシモーネ・イン ザーギ監督は4シーズン目、暫定監督を務めた2015-16シーズンを加えると5シーズン。セリエAでは異例の長期政権だ。システムは[3-5-2]だが、3バックはフラットで、当然かつてのリベロはいない。中盤中央はアンカーにルーカス・レイヴァ、インサイドハーフにルイス・アルベルト、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチという攻撃的な構成になっている。
アンカーに起用されているブラジル人、ルーカス・レイヴァは屈強な守備型ではなく、的確にボールを散らしていく深い位置にいるプレイメイ カータイプ。スペイン人のルイス・アルベルトはこのチームの攻撃におけるクリエイターで、数多くのアシストを記録している。ルイス・アルベルトと反対側の右インサイドハーフのミリンコビッチ・サビッチやマルコ・パローロも攻撃型である。クリエイティブなインサイドハーフを2人並べること自体、セリエAでは珍しいのだが、そこにインザーギ監督の攻撃への意欲が読み取れる。
FWはチーロ・インモービレが絶対的なエース。23試合で25ゴールをゲットし、クリスティアーノ・ロナウド(ユヴェントス)、ロメル・ルカク(インテル)を抑えて得点王レースの首位を快走中だ。パートナーのフェリペ・カイセド、ホアキン・コレアはいずれもエクアドル、アルゼンチンの代表選手。インモービレの縦に出てシュートへ持っていく強さを生かすべく、スペースを失わないうちに縦へ早く攻め込むことが重視されている。
快進撃で脚光浴びるアタランタ カギは「人」を抑える守備
近年目覚ましい躍進を遂げるアタラ ンタ。今季もその勢いは止まらない photo/Getty Images
続きを見る
アタランタもラツィオと同じ3バックだが、シンプルに個の強さをオーソドックスなスタイルの中で生かしていくラツィオとは違い、システマティックな攻守が際立っている。
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が率いるアタランタは、常に勝ちに近い試合ができるチームに仕上がった。勝ちに近いというのは、敵陣でのプレイ時間の長さゆえだ。5レーンを意識した無駄のない配置とパス&ムーブによって、ビルドアップ段階では常に数的優位を作り、それを利用してボールを運ぶ。そして、敵陣へ攻め込んだ後は、ボールを失うと即座にマンツーマンによるハイプレスで早期の奪回を狙う。この攻守の循環が上手くいくと、アタランタは敵陣でのプレイ時間が長くなる。多くのチャンスを作る条件が整うだけでなく、マンマークのハイプレスが機能すれば敵陣でボールを奪えるのでそれも攻撃面で大きなプラスになる。
アタランタは個々のタレントでインテル、ユヴェントスだけでなくラツィオと比べても見劣りしているが、チームとしての機能性で補っている。 ビルドアップは定型ではなくランダムに近く、そのため相手からすると的が絞りにくくハイプレスをかけにくくなっている。攻撃ではサイドに起点 を作り、そこでトライアングルを形成して変化させることでボックス近くまで侵入する仕組みを持っている。
攻撃を牽引するのは小柄なテクニシャン、アレハンドロ・ゴメスと左利きのヨシップ・イリチッチだ。この 2人が[3-4-2-1]の2シャドーでプレイし、彼らの技術と着想からチャンスを作っていく。他の選手は基本的にハードワーカーだ。特別な武器はないかわりに、ガスペリーニ監督のアイデアを豊富な運動量で体現していく。
ハイプレスで「人」を抑えにいくアタランタ。激しい寄せでボールを奪う photo/Getty Images
続きを見る
アタランタはマンツーマンでのハイプレスが脚光を浴びているが、これ自体は新しい戦術というわけではない。
敵陣でハイプレスを行う場合、「人」を抑えていく形と「ボール」の位置と状態からポジションを決めていく形のどちらかになる。実際には両者をミックスするのだが、メインをどちらにするかという点で、ガスペ リーニ監督は「人」を選択したわけだ。
バルセロナやリヴァプールもハイプレスはするが、アタランタほど「人」にフォーカスしていない。ガスペリーニに最も近いのはマルセロ・ ビエルサ監督で、ビエルサも明確に「人」を抑えていく形のハイプレスである。2015-16シーズンにラツィオの監督に就任したが、2日で辞任 している。もしビエルサがそのままラツィオの監督を務めていたら、ガスペリーニより前にマンマークのハイプレスで注目されていただろう。
「人」にフォーカスしたハイプレス は、外されたときのリカバーが難しく、 アタランタはときどきカウンターに苦しめられている。また、ボールにフォーカスしたプレスに比べると明確に運動量に依拠しているので、このタイプはシーズン後半に息切れする傾向はある。それをどう乗り越えていくか。これこそがアタランタの最終順位を左右するのではないだろうか。
これまで守備重視の戦術を採用するチームが多かったイタリアで、 今度は攻撃に比重を置いたチーム が頭角を現し始めた。これこそ今シーズン、セリエAが変わりつつある証左と言える。
文/西部 謙司
※theWORLD(ザ・ワールド)242号、2019年2月15日発売の記事より転載
●最新情報をtwitterで見よう!
twitterアカウント
https://twitter.com/theWORLD_JPN/




![[特集/躍動するサムライ18 02]ビッグクラブも無視できない “闘うプレイ”でクラブを導くサムライMF](https://www.theworldmagazine.jp/wp-content/uploads/2025/03/31e010ea77d697ed6c0c3a9fb6841664-240x240.jpg)
![[特集/躍動するサムライ18 01]得点という結果で違いを作る! 7人のサムライ・アタッカー](https://www.theworldmagazine.jp/wp-content/uploads/2025/03/c5ebd5812b2b164724140e72cf1ef37e-240x240.jpg)